2023年7月某日、広島県の小学校の教員研修に呼んで頂きました。
貴重な機会を頂きまして誠にありがとうございました!
解説だけでなく体験も含めて「科学的根拠に基づいた授業作り」についてお話しました。
昨年8月末に出版した本をベースにしたお話です。

2023年7月某日、広島県の小学校の教員研修に呼んで頂きました。
貴重な機会を頂きまして誠にありがとうございました!
解説だけでなく体験も含めて「科学的根拠に基づいた授業作り」についてお話しました。
昨年8月末に出版した本をベースにしたお話です。

翻訳しました!効果的な学習方法は6つ!
ようやく願いが叶いました。
協力して下さった皆様、ありがとうございました!
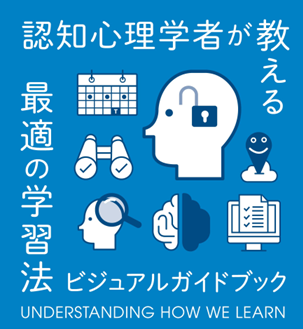
Institute for effective education(IEE)が作成した資料を日本語に翻訳しました!
教育分野のエビデンスに関する資料の多くは学術的であり,
学校の先生の支援につながる資料ではありませんでした。
エビデンスを学校で利用できるように,
IEEは学校の先生方に向けて資料を作成・公開しています。
どちらの資料も学校の先生に向けて執筆された資料です。
エビデンスの種類とそれぞれの特徴・注意事項を紹介しています。
特に6ページ目が参考になると思います。
原著:Engaging with evidence guide
日本語に翻訳した資料はコチラをご覧下さい。
エビデンスの作り方を紹介しています。
授業方法の効果を知りたいと思った時,本書が役立つと思います。
日本語に翻訳した資料はコチラをご覧下さい。
注:IEEは2020年12月に閉鎖されました。
EEFやWWC以外にもエビデンスを紹介している機関があったのでご紹介します。
ヴァンダービルト大学
[Resources] から [Evidence-based Practice Summaries]を選択
ジョンズ・ホプキンズ大学
ミズーリ大学
[Evidence Based Intervention Section]から[Intervention]を選択
American Institutes for Research(AIR)
[Tool chart ]から[Academic Intervention Tools Chart]を選択
ジョンズ・ホプキンズ大学
2020年12月に閉鎖
“Evidence”をキーワードにして海外の教育機関・洋書・論文を調べ続けた結果,海外の教育分野でエビデンスの参照が浸透している理由が少しずつ分かってきました。主な理由は以下の3つに分けることができそうです。
1.社会経済的な理由に関係なく質の高い教育を提供する
2.教育神話と決別する
3.学習に苦労している子どもの支援
国内の様子を見ていると「経験に基づいた教育」が批判の的にされていて,「経験」に基づいてはいけない雰囲気です。海外では日本のように「経験」を拒絶していません。批判するどころか,とても大切にしていました。「教育政策」の話と「教育実践」の話を分けていないため,誤解が誤解を呼んでいる気がしています。
日本では「エビデンスに基づく教育」の是非について哲学・議論している文献がとても多い。一方で,「どのようにエビデンスを授業に利用したら良いのか」など,具体的な方法を説明している(日本語で読める)本や論文は極めて少ない状況です。
「教育分野のエビデンスの使い方」について学びたくても学べない状況を何とかしたくて,いろいろ模索している状況です。良い洋書をいくつか見つけることができたことは幸いでした。教育分野に強い翻訳家さんと仕事のお話がしたい。
2016年頃からEBPM(Evidence-based policy making)というワードをよく見聞きするようになりました。右へ行くのか?左へ行くのか?進む道を決める時,経験や勘だけでなくエビデンスも参照した上で決めようとする考え方を意味しています。エビデンスに基づいて政策を考えようとする動向は1970年頃から現れており,1990年頃から強く推されるようになりました。
“Evidence-based”という考え方は医療の領域から始まっています。昔は(権威的な)医者の経験に基づいて治療が決められていて,科学的根拠なんてなかった。例えば,コチラの本(過去の医療がここまで危険だったとは!)。明らかに間違っている治療方法なのですが,当時は「偉い先生が言うのなら間違いないだろう」ということで(疑われることなく)効果がある治療として行われていたのかもですね。
「エビデンス(根拠)」という言葉からイメージされることは個人間で異なるため(?),誤解が生じている部分もあるようです。「エビデンス(根拠)」と聞くと,「楽しかった!等の感想」や「子どもたちの目の輝き」もエビデンスに含まれるように感じてしまうのですが,“Evidence”を学術的に扱っている世界では,もっと限定的な情報をエビデンスとして定義しています。因果関係(信頼性・妥当性)が担保できるデザインで検証された情報がエビデンスであり,データ収集の方法を設計していない街角アンケート等はエビデンスではなく,ファクトやデータとして扱われます(質の低いエビデンスとして認識されることもあります)。
“Evidence”を扱っている世界では,「エビデンス」の意味は世間的なイメージと異なるので,「エビデンス」という言葉を使う時は要注意。「エビデンス」は「情報」だけど,「情報」は「(厳密に定義している)エビデンス」と等価ではないので,「単なるデータ」を「エビデンス」と言ってしまうとエビデンス警察に捕まるとか,捕まらないとか。
エビデンスの質に高・低がある理由は,「因果関係を重視しているから」に尽きます。「因果関係が推定できる」ことが大切なので,データを収集する方法は極めて慎重に設計されます。「(雑な方法で得られた)データはある。統計分析で何かわからないか?」という質問に対して「無理です」とデータサイエンティストに冷たく返答される理由はこのあたりではないでしょうか。どれほど高度な統計分析を施したとしても設計段階で失敗しているのであれば,統計分析しても分かることは多くありません。
「科学的根拠も意思決定の判断材料として扱いましょう」ってことを主張していたわけですが,“-based”という表現は,「エビデンス(科学的な根拠)だけを使って意思決定しましょう」という過激な(?)印象を与えてしまった(誤解を招いてしまった)ようです。エビデンス系について勉強し始めた時,全く同じ誤解をしていました。「科学的に実証されている方法だけを実践で使う」ことを意味しているのかな?と思っていた時期がありました。このような誤解を招いてしまった反省から,“-based”ではなく“-informed”という表現が使われるようになったみたいです。
“Evidence-informed”という表現は“-based”をやわらかくした感じです。「経験や勘で意思決定するな!科学的根拠に基づいて考えろ!」(based)ではなくて,「経験や勘も大切だよね。これまでの実践経験の他に,エビデンスも参照して意思決定しない?その方が良いかもよ?」(informed)みたいな感じでしょうか(意訳&誤訳,スミマセン。エビデンス警察に捕まるかしら?)。
エビデンスを強く主張しない,やわらかい印象を与える表現の方が誤解されることなく,浸透しやすいのかもしれないですね。どちらにしても,“-based”なのか“-informed”なのか,専門用語の峻別は重要なことではなさそうです。
コチラの記事がとても参考になりました。教育政策はこのようなプロセスで決められていたのか・・・。
“経済財政諮問会議の議事録を読むと、財政、金融、経済政策に関する話題では、それなりにデータに基づく現状分析が行われ、経済学的に見て妥当な議論が行われている。ところが、教育再生に話題が及ぶと、多くの委員が「私の個人的な意見ではあるが」とか「私の友人で、ある学校の校長をしている人の話によると」とか「わが社の例では」などのように、個人的な体験に基づく主観的な議論を展開し始めている。”
「教育の方針を決定する時の根拠が各個人の経験に基づいていること」が望ましくない。莫大な予算を投じて全国レベルで改革をするわけですから,失敗できないし,できるだけ効果最大な方法を選択したいはず。しかし,「効果的な方法である根拠」は「個人の経験」。確かに良くない。絶対に良くない。冒頭で書いた「初期の医療」とまでは言えないけれど,ちょっと危険な印象を持ってしまいます。
「エビデンスに基づいた教育政策」も上記の内容と同様です。「意思決定する際,経験や勘だけでなく,エビデンスも参照しよう(エビデンスが無いのなら作ってみよう・検証してみよう)」という考え方が背景にあります。エビデンスが得られている教育方法を一般化・スタンダード化しようとする政策では決してないはず。
教育分野でも「データを扱っている」=「エビデンスに基づいている」という理解になっている傾向があるような,ないような。混乱を招いてしまうのではないかしら?ちょっとだけ心配しています。
教育政策レベルだけでなく,教育現場レベルでもエビデンスを活用しているケースが海外で起きているようです。イギリスでは,学校の先生たちが集まって教育系エビデンスの活用やリサーチリテラシーの育成に関するカンファレンスを開いているのだとか。最近読んだ本(What Works Now? Evidence-Informed Policy and Practice)の中でresearchEDが紹介されていました。「教室の実践」と「教育研究」をつなぐことがresearchEDのミッションとのこと。イギリスの教育現場レベルでも,“-based”ではなくて“-informed”な考え方が浸透している模様(「実践知」と「エビデンス」を統合して意思決定することが理想とされている)。
教育現場にエビデンスを浸透させるためには,researchEDのような組織を作ることも良い選択肢だと思うのですが,仕事が忙し過ぎて参加者が集まらない気もします。教員養成段階から教育科学に関するリテラシーを組み込んでおく方が良さそうと思っているところです。推測になるのですが,教育科学に関するリテラシーを教えている教育学部・教職大学院は今のところ無さそうです。
「科学的根拠に基づいていない教育は間違っている」という過激な主張として誤解されていることが浸透しない大きな原因なのかもしれません。「科学的な根拠に基づいていない教育は間違っている」という過激な主張は絶対に言っていない(言っていたとしたら,超特大ブーメランになって自分のところへ帰ってくる)。例えば,大学の授業で「科学的根拠に基づいていない教育は間違っている」と言ってしまうと,「この授業はすべてエビデンスに基づいているのか?」と返されて詰みます。
「科学的な根拠が得られている教育方法をスタンダードにしよう」という考え方も誤解です。子どもの心が置き去りにされているし,どこの学校へ行っても全く同じ授業をしていることになります。
「教育の効果は数値で測れない(測るべきではない)」という主張もよく見聞きします。数値に焦点が集まってしまったら,授業方法がスタンダード化されてしまって,教室から「学びの面白さ・楽しさ(子どもたちの目の輝き)」が失われるのではないかという危惧。可能性はゼロではないけれど,過剰な危険視ではないかなと感じています。
教育現場でもPDCAの考え方は広がっているけれど,Check(評価)は偉い人や担当した個人の主観的評価です。偉い人の気分で評価されたり個人的なモノサシで評価するよりも,客観的な方法で評価される方が公平です。さらに,客観的な指標を使って同一軸上で比較する方が,より良いAction(改善)につながりやすい気もします。ただ,個人で評価指標を準備するのは難しいですよね。このあたりは評価指標を自治体レベルで統一しておく方が良さそうです。例えば,埼玉県の学力調査はとても良い事例です。順位(偏差値)からの脱却(項目反応理論を利用)。データ活用の支援。すごいです。
「エビデンスの活用」は学術論文が読める学術的な専門知識が必要だけど,「データの活用」はそこまで求められないので,「データの活用」の方が先に現場に浸透しそうです。
教育系のエビデンスの話は大きく分けて3つありそうです(個人的な印象です)。
(1)教育政策:EBPM系の話題の1つ
(2)教育現場:エビデンスの活用が主なテーマ
(3)データ活用:学力調査とICT導入の掛け合わせ
調べ始めた当初は(2)の情報を主に集めていました。サンプル数1の経験談ではなくて,現場で使える武器(エビデンスを教育に活用できるスキル)を学生さんたちに提供したくて。調べていると教育政策系も「エビデンス」を扱っていることが分かり,(1)にも手を伸ばしました。資料を読んでいると,「エビデンス」と言うより「データの活用」の話では?と思われる情報に混乱してしまって(3)も調べ始めました。どこへ向かっているのか迷子になりそうです。
取り組んでいる方々もそれぞれの領域間で異なっています。
(1)教育政策:政策科学系・経済学系・教育科学系の専門家・地方自治体
(2)教育現場:教育現場の先生・教育関係者
(3)データ活用:評価系・教育工学系の専門家・地方自治体
それぞれの話を理解しようと思うと,それぞれ異なる知識が必要です。
(1)教育政策:計量経済学,開発経済学,労働経済学,政策科学,心理学,学習科学
(2)教育現場:エビデンスに基づいた医学(EBM),エビデンスの活用
(3)データ活用:項目反応理論等のテスト理論,ラーニングアナリティクス
関連する本(和書・洋書)を買い漁って少しずつ読み進めている最中です。書籍に投じた金額は過去最高(洋書は高いよ)。調べ始めた1年前に比べたら理解は少し深まった気がするので「良し」としたい。
何もわからなかった当時,こちらの研究会が主催するセミナーに初めて参加させて頂き,色々なことを教えてもらいました。エビデンスを扱う様々な領域の専門家が集まる国内唯一の場所です。様々な領域の専門家の話を聞くことができたので大変有意義でした。
追加(2020年7月)
日本評価研究に論文が掲載されました。
エビデンス仲介機関(教育分野)の特徴を整理しています。

国:アメリカ
機関:Institute of Education Sciences (IES)
背景:NCBL法(2002年)の成立がエビデンスの需要を高めた
研究内容をわかりやすい言葉で教育関係者に伝える仕組みが必要だった
目的:最も有効な施策・取り組みの情報提供・意思決定を支援する
特徴:エビデンスの質を保証するために厳密な基準で分類される
最新の研究を迅速にレビューしている(Quick Review)
利用しやすい実践的なガイドを発表(Practice Guide)
備考:「(信頼の高いエビデンスに基づいて)教育的介入の因果関係が明示されるべきである」という考え方がある(豊, 2011)。WWCのエビデンス基準を満たす施策のみを採用せよということではない。NCLB法はエビデンスに基づいた施策の採用を求めているが,実際にどのような施策を科学的根拠があると判断するかは現場に委ねられており,WWCはあくまで参考情報というのが教育省の立場である(田辺, 2006)。
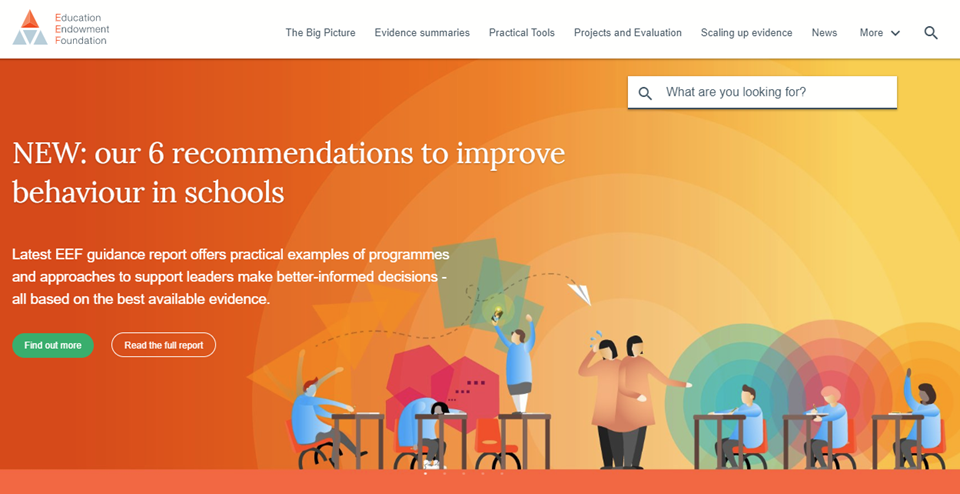
国:イギリス
機関:ロンドン大学(教育研究所)
背景:(1) 社会経済的に不利な子どもの学力不振の解決
(2) 教育省から教育基金財団(EFF)が1億2500ポンドの出資を受けて設立
目的:(1) 環境的に不利な子どもたちの学力向上の支援
(2) 教員の専門性の向上(エビデンスの有用性の理解・エビデンスの適用)
特徴:Teaching and Learning Toolkit
5歳から16歳までの教育に関するエビデンスを要約
各効果を「費用(資金)・エビデンスの強さ・インパクト」で表示
備考 (1):インパクトはエフェクトサイズを示している
備考 (2):EEF は教員の専門性の向上を活動の指針としている。実際の教育現場で行われる教育研究から得られたエビデンスの有用性を教員が理解し,自ら最適な活用方法を判断した上で,教育現場での実践へ適切に活用することをもって,専門職たる教員が有効にエビデンスを「つかう」ことと位置づけている。そのため,教員に強制的にエビデンスを踏まえた実践を行うよう命令したり,強く指導したりするアプローチは取られておらず,教員の行動変容を促すことが意識されている(三菱UFJ&コンサルティング, 2017)。
三菱UFJ&コンサルティング (2017). 平成28年度 生涯学習施策に関する調査研究諸外国における
客観的根拠に基づく教育政策の推進に関する状況調査報告書 文部科学省
田辺智子. (2006). エビデンスに基づく教育 日本評価研究, 6 (1), 31-41.
豊 浩子. (2011). 米国のエビデンス仲介機関の機能と課題-米国 WWC 情報センターの例より
(特集 教育研究におけるエビデンス) 国立教育政策研究所紀要, 140, 71-93.
最近のコメント